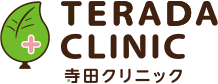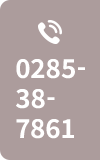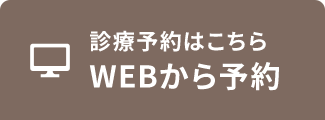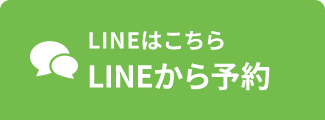むくみの起きやすいタイミング
 一般的に、夕方になると足がだるくなったり、飲酒をした翌日に顔がむくむことは日常的によく見られる症状です。このようなむくみを効果的にケアするには、むくみのメカニズムを理解し、解消法を実践することが大切になります。
一般的に、夕方になると足がだるくなったり、飲酒をした翌日に顔がむくむことは日常的によく見られる症状です。このようなむくみを効果的にケアするには、むくみのメカニズムを理解し、解消法を実践することが大切になります。
むくみ(浮腫)とは
むくみが起きる原因は、細胞と細胞の間に水が溜まることで引き起こされます。なお、むくみは、医学用語では浮腫と言います。
人の体の約60%は水分でできており、そのうち2/3は細胞の中に含まれる細胞内液で、残りの1/3は血液に含まれる水分や、細胞と細胞の間を満たしている細胞外液となります。これら水分は、細胞に栄養を運搬したり、老廃物を除去する役割を担っています。また、細胞や血管を行き来して体内の水分バランスを保つ役割もあります。
このバランスが何らかの原因によって崩れると、むくみを発症します。なお、むくみは病的なものではありません。
むくみのメカニズム
 むくみは血流が低下することで引き起こされます。血液は、私たちの体に必要な酸素や栄養を体の隅々まで運搬し、運搬し終わった後は、二酸化炭素や老廃物などを受け取って、心臓に戻っていきます。
むくみは血流が低下することで引き起こされます。血液は、私たちの体に必要な酸素や栄養を体の隅々まで運搬し、運搬し終わった後は、二酸化炭素や老廃物などを受け取って、心臓に戻っていきます。
血流は筋肉を動かすことで促進されるため、筋肉の動きが悪いと血流も滞ってむくみが現れます。例えば、長時間デスクワークをしたり飛行機に乗ったりして足がむくむのは、下肢の筋肉を動かさなかったために、足の血流が低下したことによります。
足は心臓からもっとも距離があるため、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割を果たして、血液や水分を全身に戻しています。よって、このふくらはぎの筋肉を長時間使わないでいると、次第に水分が下半身に蓄積され、足がむくんでいきます。
むくみが起きる原因
体がむくむ主な原因は以下になります。
塩分の過剰摂取
体には塩分濃度を一定に保つ機能が備わっており、塩分を過剰に摂取すると、体の塩分濃度を調節するために、余分な水分を体内に溜め込むようになり、むくみを起こします。
アルコールの摂取
血中のアルコール濃度が高くなると、血管が拡張して血管から水分が漏れ出し、むくみを起こします。
ホルモンバランス
女性の場合、月経周期によるホルモンの関係で、月経前の時期には体内に水分を溜め込みやすくなり、むくみを起こします。
これらの他にも、睡眠不足、運動不足、ストレスなど、むくみの原因は多岐に渡ります。また、むくみには一過性のものと、慢性的なものがあり、それぞれ原因が異なります。
一時的に体がむくむ原因
立ち仕事やデスクワークなど、同じ姿勢のまま長時間過ごすと、ふくらはぎが血液を心臓に戻す役割が低下し、血流が下半身に滞ってむくみとなります。さらに同じ姿勢を保つことで、足の筋肉が硬直して伸縮しにくくなることも原因です。
この他にも、塩分の過剰摂取や、アルコールの摂取、生理によるホルモンバランスの変化、睡眠不足、運動不足、ストレスの蓄積なども、一過性のむくみの原因となります。
これら一過性のむくみを改善するには、塩分やアルコールの摂取を控える、休息を取る、ストレッチをして筋肉をほぐすなどが有効です。軽度のむくみであれば、しっかり睡眠を取れば翌朝には改善していることも多いです。
慢性的に体がむくむ原因
慢性的に体がむくむ原因としては、心臓、腎臓、肝臓の疾患による可能性があります。これらが原因のむくみの特徴は、慢性的にむくみの症状が現れ、むくんでいる部位を押すと指の後がつくなどがあります。このような症状がある場合は、できるだけ早期に医療機関を受診するようにしましょう。
臓器の疾患以外では、栄養バランスの乱れによる栄養失調、ふくらはぎの血管が膨らむ下肢静脈瘤、手術でリンパを取り除いた際に生じるリンパ浮腫なども考えられます。
むくみの原因として考えられる病気
上記の通り、病気のサインとしてむくみの症状が現れることもあります。むくみがひどい際に第一に疑われるのが、腎臓、心臓、肝臓の疾患です。
腎機能障害(腎臓病・腎不全)
腎臓は、血液をろ過して老廃物を尿として体外に排出する役割があります。腎機能が低下すると、体内に老廃物を含んだ水分が蓄積されるため、体にむくみが起こります。
肝硬変
肝硬変とは肝臓全体が硬化する疾患で、発症すると肝臓でアルブミン等のタンパク質が合成できなくなります。アルブミンは、水分を血管内に留めておく働きがあるため、このアルブミンが低下すると、血管から水分が漏れ出し、全身のむくみが起こります。
その他のむくみの原因には、以下のようなものがあります。
栄養失調
食生活の乱れなどで栄養素の摂取量が不足し、体内のタンパク質が不足すると、血液中にアルブミンが不足して血管から水分が漏れ出し、全身にむくみを起こします。
下肢静脈瘤
下肢静脈瘤とはふくらはぎの部分の血管が膨らんで足がむくむ状態で、女性に多くみられます。病名の通りに、下半身の静脈の血管がコブのように膨らむのが特徴です。
リンパ浮腫
リンパ浮腫とは、手術でリンパ節を除去した際に、リンパの流れが滞って水分が流れなくなり、むくみますを起こした状態です。
むくみの改善方法
むくみは病気が原因ではない場合は自然に改善しますが、不快に感じるほどのむくみが起きたら、以下の方法で改善することができます。
顔のむくみの改善
 朝起きて顔がむくんでいる場合は、冷水と温水で交互に洗顔することで、血管が収縮と拡張を繰り返し、むくみが解消します。
朝起きて顔がむくんでいる場合は、冷水と温水で交互に洗顔することで、血管が収縮と拡張を繰り返し、むくみが解消します。
また、水に濡らして絞ったハンドタオルを電子レンジで1分ほど加熱して作ったホットタオルを顔に乗せて温めることで、顔の血行を促進してむくみを解消することもできます。
その他では、マッサージによって改善することもできます。滑らかなクリームを顔全体や首、手に着け、顔の中心から外に向かって、手のひらでやさしく顔をさすります。次に、耳から鎖骨にむかって首のサイドをさすります。その後、鎖骨の上にあるくぼみを、ゆっくりと押します。このように、鎖骨や首の周りのリンパ節を刺激することで、顔のむくみを改善することができます。ぜひ日々のスキンケアとともに行い、むくみを予防しましょう。
体のむくみの改善
 むくみは血液やリンパ液などの体液が停滞することで起こるため、むくみを解消するにはストレッチが効果的です。
むくみは血液やリンパ液などの体液が停滞することで起こるため、むくみを解消するにはストレッチが効果的です。
むくみやすい足の場合は、膝を曲げ伸ばす、足首をまわすなどして、凝り固まった筋肉や関節をほぐしましょう。また、つま先立ちの状態でかかとを上下すると、ふくらはぎの筋肉のポンプ作用が促進されてむくみの改善につながります。
手でマッサージすることも有効です。心臓から遠い部分から近い部分に向けて流すように行いましょう。足首やひざの裏、足の付け根など関節まわりなど、むくみやすい箇所を重点的に行なうと良いでしょう。
その他では、足を水平に保つことも効果的です。足のむくみは重力の影響によることが多いため、オットマンなどに足を乗せて水平を保ちましょう。また、床に寝て足を心臓より上の位置に上げることも、むくみの解消につながります。
体を温めることもむくみの改善には大切です。湯船に浸かってしっかり体を温めることで、血流が促進されたり、水圧によって滞った水分が流れるなどして、むくみの改善につながります。湯船に浸かった方が効果的ですが、足湯でも効果はあります。
栄養を摂取することもむくみを改善させます。むくみの原因の一つに塩分の過剰摂取がありますが、カリウムには、ナトリウム(塩分)を尿として体外に排出する働きがあるため、カリウムを多く含む食品をとることで、むくみを改善できます。代表的な食材は、バナナやリンゴ、メロン、野菜類などになります。ただし、腎機能が低下している場合には、カリウムの摂取を控える必要があるため、必ず担当医に相談するようにしましょう。
むくみの予防
むくみは、日常生活を少しだけ改善するだけでも予防効果があります。以下は、代表的なむくみの予防方法になりますので、ぜひ試してみましょう。
運動習慣を身につける
 運動をすると体の血行が促進されてむくみ対策になります。定期的な運動習慣を身につけることや、階段を使う、早足で歩くなど、日常生活の中でも取り入れられる運動もありますので意識してみましょう。
運動をすると体の血行が促進されてむくみ対策になります。定期的な運動習慣を身につけることや、階段を使う、早足で歩くなど、日常生活の中でも取り入れられる運動もありますので意識してみましょう。
塩分の過剰摂取を控える
体は常に体内の塩分濃度を一定に保つ機能があるため、塩分を過剰に摂取すると、体が水分を溜め込んで塩分濃度を下げようと働き、むくみにつながります。外食は塩分過多になりがちですので注意が必要です。また、自炊の場合でも、加工食品には精製された塩分が多めに含まれていますので、使用する際には表示を確認するようにしましょう。自宅に常備する塩をカリウムやマグネシウムを含むものにすることも、むくみ対策になります。
塩分を排出する機能のある栄養素を摂取する
 上記の通り、塩分の過剰摂取はむくみにつながりますので、食生活の中に塩分を排出する機能のある食材を積極的に摂ることも有効です。
上記の通り、塩分の過剰摂取はむくみにつながりますので、食生活の中に塩分を排出する機能のある食材を積極的に摂ることも有効です。
塩分の排出を促進する栄養素はカリウムです。カリウムはウリ科の野菜に多く含まれるため、スイカやキュウリ、冬瓜などは効果的です。このほかでは、あずきやバナナ・柿などの果物や、血管を緩める効果のあるマグネシウムを含む海藻類なども摂ると良いでしょう。
アルコールの過剰摂取を控える
 ビール、ワイン、お酒などのアルコール類を摂取すると、一時的に血管が広がって血行が良くなりますが、同時に喉が乾くため余計に水分を多く摂ってしまい、むくみにつながります。
ビール、ワイン、お酒などのアルコール類を摂取すると、一時的に血管が広がって血行が良くなりますが、同時に喉が乾くため余計に水分を多く摂ってしまい、むくみにつながります。
また、飲酒の際に食べるつまみは基本的に塩分が高めのため、塩分の過剰摂取によってもむくみを促進してしまいます。
定期的に休肝日をもうけるなどして、改善に努めましょう。
弾性のストッキングを着用する
弾性のストッキングやソックスはむくみ予防になります。これらを着用してふくらはぎや足首を常に圧迫することで、足の血管やリンパ管を刺激して流れを良くし、むくみを予防します。
ゆとりのある服を着用する
体の締め付けが強いものを着用すると、血行を妨げてむくみにつながります。特に、体の中心部を覆うブラジャーやガードルなどは注意が必要です。これらを着用すると、手足など、もともと血行が悪化しがちな部分にも影響が及びます。自分のサイズにあった下着を身に付けることで、むくみを軽減することが可能になります。
体を温める
 体が冷えると、血行が阻害されてむくみやすくなります。特に、むくみやすい足首からふくらはぎを冷やさないように配慮することは大切です。足を出すファッションの際は、レッグウォーマーを持参したり、薄手のストールを常備するなどして、体を冷やさない工夫をしてみましょう。
体が冷えると、血行が阻害されてむくみやすくなります。特に、むくみやすい足首からふくらはぎを冷やさないように配慮することは大切です。足を出すファッションの際は、レッグウォーマーを持参したり、薄手のストールを常備するなどして、体を冷やさない工夫をしてみましょう。
また、足が冷えてむくみを感じた日は、湯船に浸かって体を温めるか、足湯で足を温めてから就寝するように心がけましょう。